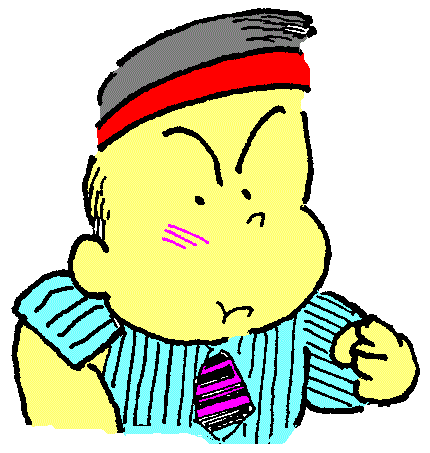 |
|
|
■ 申22号 越後線における徐行予告信号機の建植位置に関する申し入れ 2024年 4月18日申し入れ |
|
標題について、1月1日に発生した地震の影響で越後線の内野駅から新潟大学前駅間(71K740m~71K954m)において、運転再開となった1月6日から速度25Km/h以下、その後2月14日から速度45Km/h以下の徐行が施行されました。 当該徐行において、上り列車に対する徐行予告信号機が徐行信号機の292m手前に建植されており、当該区間の列車を担当する行路の乗務点呼等で「徐行予告信号機から徐行信号機までの距離が近い」ことが注意喚起されています。 「運転取扱実施基準」第224条には臨時信号機の設置方法が定められていますが、「運転取扱実施基準解説」の記載内容との整合性に疑義が生じています。 徐行速度に対する速度超過は重大事故に直結することから、規定の理解・遵守に関する疑義は解消されなければなりません。 従いまして東日本ユニオン新潟地本は下記の通り申し入れますので、新潟支社の誠意ある回答を要請します。
記
以上 |
|
■ 団体交渉の日程が決定! |
|
★ 2024年 6月18日 14時00分より団体交渉を行います |
|
■ 団体交渉を終了! |
|
★ 2024年 6月18日 14時00分より団体交渉を行いました。時間の都合により後日に議論継続として交渉を中断しました。 |
|
■ 支社側の回答及び見解 |
|
|
■ 団体交渉のポイント |
|
|
■ 第2回団体交渉の日程が決定! |
|
★ 2024年 7月10日 9時30分より団体交渉を行います |
|
■ 第2回団体交渉を終了! |
|
★ 2024年 7月10日 9時30分より団体交渉を行いました |
|
■ 第2回団体交渉のポイント |
|