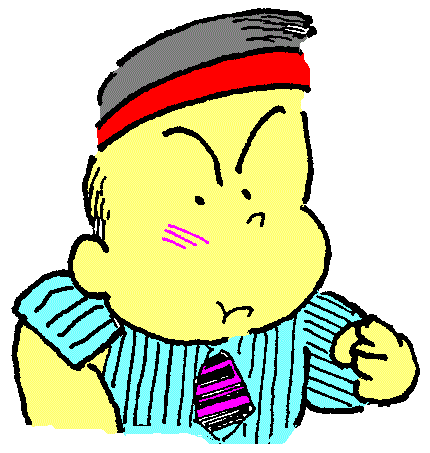 |
|
|
■ 申11号 「在来線保線部門の将来ビジョンの実現に向けた組織の見直しについて」に関する申し入れ
2025年 5月 2日申し入れ
|
|
表題について2025年4月17日に提案を受けました。今提案の目的は「経営環境の変化を踏まえ、スピード感を持って柔軟に業務を推進すると共に、活躍フィールドを広げることである」と認識しています。厳しい経営環境の中で10年先を見据え、今施策で提案をされている現業機関の見直しや、組織の融合と連携を行っていく事は理解しますが、施策を担う社員の安全・健康・ゆとりが担保され、そして社員の技術力の向上や働きがいが実現されなければなりません。 提案以降、社員から東日本ユニオンに多くの疑問の声が寄せられており、現場視点での社員の理解・納得が必要不可欠なことから、下記のとおり申し入れますので、新潟支社の真摯な回答を要請します。
記 「変革2027」の実現に向けて
「将来ビジョンの実現に向けた組織の見直し」
以上 |
|
■ 団体交渉の日程が決定! |
|
★ 2025年 5月23日 10時00分より団体交渉を行います |
|
■ 団体交渉を終了! |
|
★ 2025年 5月23日 10時00分より団体交渉を行いました |
|
■ 支社側の回答及び見解 |
|
「変革2027」の実現に向けて
「将来ビジョンの実現に向けた組織の見直し」
|
|
■ 団体交渉のポイント |
●本社提案「JR東日本グループのさらなる飛躍に向けた新たな組織と働き方について」の影響について ・2025年6月20日実施の「在来線保線部門の将来ビジョンの実現に向けた組織の見直し」について、今回の組織再編に伴う変更点はない
●教育・育成について ●「将来ビジョンの実現に向けた組織の見直し」 |