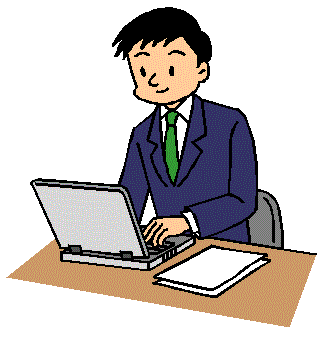 |
|
|
■ JR東日本が第2四半期決算を発表 5期連続増収増益 |
|
JR東日本は10月30日に、2026年3月期の第2四半期決算を発表しました。 これによると、連結・単体ともに5期連続で増収増益となりました。 セグメント別では、不動産販売の時期ずれの影響による利益減などで「不動産・ホテル事業」が増収減益となったほかは、全てのセグメントで増収増益となりました。 第2四半期まで営業利益は計画を大きく上回って推移し、決算実績や今後の見通しを踏まえ、2025年度通期の業績予想は、今年4月に公表した内容を上方修正しました。 また通期62円としていた今期の配当予想も、通期70円(うち中間35円)に増配するとしました。 JR東日本第2四半期決算 (単体) ● 営業収益 10,756億円 (対前年104.8%) ● 営業利益 1,939億円 (対前年 99.0%) ● 経常利益 1,790億円 (対前年100.9%) ● 中間純利益 1,452億円 (対前年115.4%) |
|
■ 景気判断は「緩やかに回復している」に据え置き ~10月の月例経済報告~ |
|
政府は10月29日に2025年10月の月例経済報告を発表しました。 これによると景気の総括判断は、「米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している」として据え置きました。 また海外経済についても、「持ち直しが緩やかになっており、一部の地域において足踏みが見られるほか、関税率引き上げに伴う駆け込み需要やその反動の影響、不透明感がみられる」として据え置きました。 項目別では「倒産件数」について、前月までの「おおむね横ばいとなっている」から「このところ増加がみられる」に下方修正しました。 「住宅建設」は、「建築物省エネ法等改正に伴う駆け込み需要の反動もあり、このところ弱含んでいる」から「このところ弱含んでいる」へ表現を改めました。 前月に上方修正した「個人消費」は「持ち直しの動きが見られる」、「設備投資」は「緩やかに持ち直している」で据え置きました。 「輸出」は「おおむね横ばいとなっている」、「輸入」は「持ち直しの動きがみられる」で、いずれも据え置きました。 先行きについては引き続き「米国の通商政策の影響による下振れリスクには留意が必要」として、「金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要がある」との表現を維持しました。 |
|
■ 消費者物価指数は49ヶ月連続でプラス 上昇幅は拡大 |
|
総務省は10月24日に2025年9月の全国消費者物価指数を発表しました。 これによると、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は111.4で、前年同月比で2.9%上昇しました。 消費者物価指数のプラスは49ヶ月連続で、伸び率は前月の2.7%から拡大しました。 生鮮食品を除く食料は8.0%から7.6%に上昇幅が縮小したものの、上昇は14ヶ月連続となりました。 コメ類は前年同月比49.2%上昇で前月の69.7%を下回りました。 エネルギー関連では電気代が3.2%、都市ガスは2.2%の上昇で、いずれもプラスに転じました。 このほか、コーヒー豆が64.1%、鶏卵が15.2%上昇するなどしました。 指数の対象となる522品目のうち400品目で上昇、89品目が下落しました。 |
|
■ 2025年の賃金改定率4.4%、2年連続で平均1万円超え |
|
厚生労働省は10月14日に、2025年の賃上げに関する実態調査の結果を公表しました。 これによると、ベースアップや定期昇給による月額所定内賃金の平均引き上げ額は、社員1人あたり平均1万3601円となりました。 前年の1万1961円より1640円高く、2年連続で改定額が1万円を超えました。 改定率はプラス4.4%で、金額、率ともに3年連続で前年を上回り、いずれも過去最高となりました。 調査は今年7~8月に、従業員100人以上の民間企業を対象に行われ、1847社が回答しました。 規模別の改定率は、従業員5000人以上の企業でプラス5.1%、100~299人ではプラス3.6%でした。 従業員1人当たりの平均賃金を「引き上げた・引き上げる」とした企業の割合は91.5%で、前年の91.2%を上回りました。 |
|
■ 街角景気は0.4ポイント上昇 景気は、持ち直しの動きが見られる ~9月の景気ウオッチャー調査~ |
|
内閣府は10月8日に2025年9月の景気ウオッチャー調査を発表しました。 これによると9月の景気実感を示す現状判断指数(季節調整値)は前月から0.4ポイント上昇した47.1となり、5ヶ月連続のプラスとなりました。 指数の内訳としては、家計動向関連が前月から0.3ポイント上昇して46.6、雇用動向関連は2.6ポイント上昇の48.4となった一方で、企業動向関連が0.5ポイント低下の48.0となりました。 ウオッチャーの見方は「景気は、持ち直しの動きが見られる」で据え置きました。 先行きの判断指数は前月比1.0ポイント上昇した48.5となり5ヶ月連続のプラスとなりました。 価格上昇や米国の通商政策の影響を懸念しつつも、持ち直しの動きが続くとみられるとしています。 |
|
■ 名目賃金は44カ月連続で上昇 実質賃金は8カ月連続のマイナス 8月毎月勤労統計調査 |
|
厚生労働省は10月8日に、令和7年8月の毎月勤労統計調査(速報)を発表しました。 これによると、名目賃金に当たる現金給与総額は前年比で1.5%増の30万0517円で44カ月連続のプラスとなりました。 給与総額のうち、所定内給与は前年比2.1%増の26万8202円で、前月に引き続き2%を超える増加となりました。 残業代などの所定外給与は1.3%増の1万9676円、賞与などの「特別に支払われた給与」は1万2639円で10.5%のマイナスとなりました。 物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金は前年比1.4%減となり8カ月連続のマイナスとなりました。 |
|
■ 一致指数2カ月連続のマイナス 基調判断は「下げ止まり」に据え置き ~8月の景気動向指数~ |
|
内閣府は10月7日に2025年8月の景気動向指数の速報値を発表しました。 これによると景気の現状を示す一致指数は前月比0.7ポイント低下し、113.4となりました。 一致指数の低下は2カ月連続です。 輸出数量指数や鉱工業生産指数、小売販売額などが指数を押し下げました。 一致指数の動きをベースに機械的に定義される基調判断は「下げ止まりを示している」として、据え置きました。 数カ月先の景気を示す先行指数は1.3ポイント上昇の107.4と、4カ月連続の上昇となりました。 |
|
■ 10月のさくらレポート 8地域で景気判断を据え置き、北海道は下方修正 |
|
日本銀行は10月6日に2025年10月の地域経済報告(さくらレポート)を公表しました。 各地域の景気判断について、北海道を「一部に弱めの動きがみられるが、持ち直している」から「一部に弱めの動きがみられるが、緩やかに持ち直している」に下方修正しました。 そのほかの8地域では景気の総括判断を据え置きました。 一部に弱めの動きがみられるとしながらも、全9地域で「緩やかに回復している」「持ち直している」とする総括が維持されました。 「関東甲信越」は「一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している」、「東北」は「持ち直している」として、それぞれ前回7月の表現を維持しました。 |
|
■ 8月の求人倍率は0.02ポイント低下の1.20倍、失業率は0.3ポイント悪化の2.6% |
|
厚生労働省が10月3日に発表した2025年8月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月から0.02ポイント低下した1.20倍でしました。 有効求人数が前月に比べて1.0%減少した一方で、有効求職者数は0.7%の増加となりました。 原材料や光熱費などのコストの上昇により、製造業などで求人を控える動きが出ている一方で、より良い条件で新たな職を求める動きが出ている影響で、有効求人倍率は2022年1月以来の低水準となりました。 同日に総務省が発表した労働力調査によると、2025年8月の完全失業率(季節調整値)は2.6%で、前月から0.3ポイント悪化しました。 完全失業者数は前月から15万人増加した179万人、就業者数は21万人減少して6810万人でした。 |
|
■ 景況感は2期連続の改善 先行きは悪化を見込む ~日銀9月短観~ |
|
日本銀行は10月1日に2025年9月の企業短期経済観測調査(短観)を発表しました。 これによると大企業製造業の景況感を示す業況判断指数(DI)はプラス14で、前回・6月から1ポイント改善しました。 改善は2期連続となります。 業種別では「自動車」がプラス10で2ポイントの改善となるなどしました。 大企業非製造業の業況判断DIはプラス34で前回から横ばいでした。 業種別では「宿泊・飲食サービス」でプラス26と、19ポイント悪化したなどしました。 3カ月後の景況感を予測した先行き判断DIでは、大企業・製造業が2ポイント低下のプラス12、大企業・非製造業は6ポイント低下のプラス28を見込んでいます。 |
|
■ 景気判断は「緩やかに回復している」に据え置き ~9月の月例経済報告~ |
|
政府は9月29日に2025年9月の月例経済報告を発表しました。 これによると景気の総括判断は、前月の「一部に」を「自動車産業を中心に」に表現を改め、「米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している」として据え置きました。 一方で海外経済は、「持ち直しが緩やかになっており、一部の地域において足踏みが見られるほか、関税率引き上げに伴う駆け込み需要やその反動の影響、不透明感がみられる」として据え置きました。 項目別では「個人消費」を、「消費者マインドの改善に遅れがみられるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きが見られる」から「持ち直しの動きが見られる」に上方修正しました。 また「設備投資」も、「持ち直しの動きが見られる」から「緩やかに持ち直している」として上方修正しました。 前月に「米国の通商政策等による影響が一部にみられる中で、改善に足踏みがみられる」として下方修正した「企業収益」は、「米国の通商政策等による影響が自動車産業を中心にみられる中で、改善に足踏みがみられる」として表現を改めました。 先行きについては「景気の下振れリスクには留意が必要」との表現を維持しました。 |
|
■ 消費者物価指数は48カ月連続でプラス 上昇幅は縮小続 |
|
総務省は9月19日に2025年8月の全国消費者物価指数を発表しました。 これによると、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は111.6で、前年同月比で2.7%上昇しました。 消費者物価指数のプラスは48カ月連続で、伸び率は9カ月ぶりに3.0%を下回りました。 生鮮食品を除く食料は8.3%から8.0%に上昇幅が縮小したものの、上昇は13カ月連続となりました。コメ類は前年同月比69.7%の上昇で、前月の90.7%を下回りました。 エネルギー関連では電気代がマイナス0.7%から7.0%に、都市ガスはマイナス0.9%から5.0%にそれぞれ下げ幅が拡大しました。 このほか、チョコレートは49.4%、コーヒー豆が47.6%、鶏卵が16.4%上昇するなどしました。 指数の対象となる522品目のうち450品目で上昇、92品目が下落しました。 |
|
■ 街角景気は1.5ポイント上昇 景気は、持ち直しの動きが見られる ~8月の景気ウオッチャー調査~ |
|
内閣府は9月8日に2025年8月の景気ウオッチャー調査を発表しました。 これによると8月の景気実感を示す現状判断指数(季節調整値)は前月から1.5ポイント上昇した46.7となり、4カ月連続のプラスとなりました。 指数の内訳としては、家計動向関連が1.5ポイント上昇して46.3、企業動向関連が前月から2.5ポイント上昇の48.5、となった一方で、雇用動向関連は0.3ポイント低下の45.8となりました。 ウオッチャーの見方は「景気は、持ち直しの動きが見られる」で据え置きました。 先行きの判断指数は前月比0.2ポイント上昇した47.5となり4カ月連続のプラスとなりました。 価格上昇や米国の通商政策の影響を懸念しつつも、持ち直しの動きが続くとみられるとしています。 |
|
■ 最低賃金答申、39道府県で目安超え 初めて全国で1000円超え |
|
厚生労働省は9月5日に、各都道府県の審議会が決定した2025年度の最低賃金の改定額を公表しました。 これによると、全国加重平均額で66円増の1121円となります。 中央最低賃金審議会が今年8月に、都道府県A・Bランクで63円、Cランクで64円引き上げる目安額を決定し、各都道府県の地方審議会で金額を議論していました。 39道府県で目安額を上回りました。 東京都が1226円で最も高く、次いで神奈川県が1225円、大阪府が1177円で続きます。 最も低い高知、宮崎、沖縄県で1023円となり、初めて全都道府県で1000円を超えました。 新潟県は1050円、山形県は1032円となります。 最低賃金は異議申し出などを経て正式に決定後、今年10月以降、順次適用されます。 |
|
■ 名目賃金は43カ月連続で上昇 実質賃金は7カ月ぶりのプラス 7月毎月勤労統計調査 |
|
厚生労働省は9月5日に、令和7年7月の毎月勤労統計調査(速報)を発表しました。 これによると、名目賃金に当たる現金給与総額は前年比で4.1%増の41万9668円で43カ月連続のプラスとなりました。 給与総額のうち、所定内給与は前年比2.5%増の27万0827円で、前月に引き続き2%を超える増加となりました。 残業代などの所定外給与は3.3%増の2万0223円、賞与などの「特別に支払われた給与」は12万8618円で7.9%のプラスとなりました。 物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金は前年比0.5%増となり7カ月ぶりにプラスに転じました。 |
|
■ 一致指数2カ月ぶりのマイナス 基調判断は「下げ止まり」に据え置き ~7月の景気動向指数~ |
|
内閣府は9月5日に2025年7月の景気動向指数の速報値を発表しました。 これによると景気の現状を示す一致指数は前月比2.6ポイント低下し、113.3となりました。 一致指数の低下は2カ月ぶりです。 投資財出荷指数や耐久消費財出荷指数、輸出数量指数などが指数を押し下げました。 一致指数の動きをベースに機械的に定義される基調判断は「下げ止まりを示している」として、前月から据え置きました。 数カ月先の景気を示す先行指数は0.8ポイント上昇の105.9と、3カ月連続の上昇となりました。 |
|
■ 7月の求人倍率は前月から横ばいの1.22倍、失業率は0.2ポイント改善の2.3% |
|
厚生労働省が8月29日に発表した2025年7月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月から横ばいの1.22倍でしました。 有効求人数が前月に比べて0.2%減少した一方で、有効求職者数は0.0%の微減となりました。 同日に総務省が発表した労働力調査によると、2025年7月の完全失業率(季節調整値)は2.3%で、前月から0.2ポイント改善しました。 完全失業者数は前月から変わらず8万人減少した164万人、就業者数は1万人減少して6831万人でした。 |
|
■ 景気判断は「緩やかに回復している」に据え置き ~8月の月例経済報告~ |
|
政府は8月27日に2025年8月の月例経済報告を発表しました。 これによると景気の総括判断は、「米国の通商政策による影響が一部見られるものの、緩やかに回復している」として表現を据え置きました。 一方で海外経済は、「持ち直しが緩やかになっており、一部の地域において足踏みが見られるほか、関税率引き上げに伴う駆け込み需要やその反動の影響、不透明感がみられる」として据え置きました。 項目別では、「企業収益」を「改善しているが、通商問題が及ぼす影響等に留意する必要がある」から「米国の通商政策等による影響が一部にみられる中で、改善に足踏みがみられる」として下方修正しました。 「住宅建設」も「おおむね横ばいとなっている」から「建築物省エネ法等改正に伴う駆け込み需要の反動もあり、このところ弱含んでいる」に下方修正しました。 一方で「公共投資」は「底堅く推移している」から「堅調に推移している」として上方修正しました。 そのほか「個人消費」「設備投資」「輸入」「輸出」などはいずれも判断を据え置きました。 先行きについては「下振れリスクには留意が必要」との表現を維持し、金融資本市場の変動などの影響に引き続き注意する必要があるとしました。 |
|
■ 消費者物価指数は47カ月連続でプラス コメ類は上昇幅の縮小続く |
|
総務省は8月22日に2025年7月の全国消費者物価指数を発表しました。 これによると、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は111.6で、前年同月比で3.1%上昇しました。 消費者物価指数のプラスは47カ月連続で、伸び率は8カ月連続で3.0%を上回りました。 生鮮食品を除く食料は8.2%から8.3%に上昇幅が拡大、上昇は12カ月連続となりました。コメ類は前年同月比90.7%の上昇で、前月の100.2%を下回りました。 このほか、チョコレートは51.0%、鶏肉が9.3%上昇するなどしました。 エネルギー価格は0.3%下落し、前月の2.9%上昇からマイナスに転じました。ガソリン価格が1.3%下落したほか、電気代、都市ガス代ともにマイナスとなりました。 指数の対象となる522品目のうち414品目で上昇、74品目が下落しました。 |
|
■ 大手の夏のボーナスは昨年比4.23%増の94万円 過去2番目の高さ |
|
経団連は8月8日に、大手企業の2025年夏の賞与・一時金の最終集計を発表しました。 これによると、組合員の平均妥結額は加重平均で昨年と比べ3.44%増の97万4000円でした。 4年連続の増加で、現行の集計方法を採用した1981年以降で過去最高の水準となります。 これまでは2018年夏の95万3905円が最高でした。 このうち製造業119社の平均は4.73%増の102万9479円と、初めて100万円を超えました。 非製造業は35社の平均で3.3%増の86万3726円でした。 |
|
■ 街角景気は0.2ポイント上昇 景気は、持ち直しの動きが見られる ~7月の景気ウオッチャー調査~ |
|
内閣府は8月8日に2025年7月の景気ウオッチャー調査を発表しました。 これによると7月の景気実感を示す現状判断指数(季節調整値)は前月から0.2ポイント上昇した45.2となり、3カ月連続のプラスとなりました。 指数の内訳としては、家計動向関連が0.4ポイント上昇して44.8、となった一方、企業動向関連が前月から0.1ポイント低下の46.0、雇用動向関連も0.4ポイント低下の46.1となりました。 ウオッチャーの見方は「景気は、持ち直しの動きが見られる」に引き上げました。 先行きの判断指数は前月比1.4ポイント上昇した47.3となり3カ月連続のプラスとなりました。 価格上昇や米国の通商政策の影響を懸念しつつも、持ち直しの動きが続くとみられるとしています。 |
|
■ 一致指数2カ月ぶりのプラス 基調判断は「下げ止まり」に据え置き ~6月の景気動向指数~ |
|
内閣府は8月7日に2025年6月の景気動向指数の速報値を発表しました。 これによると景気の現状を示す一致指数は前月比0.8ポイント上昇し、116.8となりました。 一致指数の上昇は2カ月ぶりです。 半導体関係の交渉による輸出数量指数や鉱工業生産指数の改善、小売販売額などが指数を押し上げました。 一致指数の動きをベースに機械的に定義される基調判断は「下げ止まりを示している」として、前月から据え置きました。 5月の基調判断は、速報値では「悪化を示している」として、前月から下方修正したものの、改定値で「下げ止まり」に上方修正していました。 数カ月先の景気を示す先行指数は1.3ポイント上昇の106.1と、2カ月連続の上昇となりました。 |
|
■ 名目賃金は42カ月連続で上昇 実質賃金は6カ月連続のマイナス 6月毎月勤労統計調査 |
|
厚生労働省は8月6日に、令和7年6月の毎月勤労統計調査(速報)を発表しました。 これによると、名目賃金に当たる現金給与総額は前年比で2.5%増の51万1210円で42カ月連続のプラスとなりました。 給与総額のうち、所定内給与は前年比2.1%増の27万0244円で、前月に引き続き2%を超える増加となりました。 残業代などの所定外給与は0.9%増の1万9575円、賞与などの「特別に支払われた給与」は22万1391円で3.0%のプラスとなりました。 物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金は前年比1.3%減となり6カ月連続でマイナスとなりました。 |
|
■ 厚労省の中央審議会が最低賃金63円増を答申、全都道府県で1000円超へ |
|
厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会は8月4日に、2025年度の最低賃金について63円を目安に引き上げるよう答申しました。 引き上げ額の目安は、経済情勢に応じて各都道府県を3分類して提示します。 東京都、神奈川県、埼玉県などのAランクと、新潟県、長野県、福島県などのBランクが63円だった一方で、青森県、岩手県、山形県などのCランクが64円となりました。 Cランクが、経済力が強いA、Bランクを上回る逆転現象は初めてで、地域間格差の是正や、地方でより人手不足が深刻化している状況などが考慮されました。 引き上げ額を時給で示す現在の方式となった2002年度以降で過去最大の引き上げ幅で、目安通りに改定されれば、全国平均の時給は1055円から1118円に引き上げられます。 答申通りに引き上げられれば、一番高い東京都は1163円から1226円、最も低い秋田県で951円から1015円となり、全都道府県で1000円を超えます。 新潟県は1048円、山形県で1019円に改定される見込みです。 今後、目安を踏まえた上で各都道府県の審議会で引き上げ額を決定し、10月頃から新たな最低賃金が適用されます。 |
|
■ 6月の求人倍率は前月と0.02ポイント低下の1.22倍、失業率は4カ月連続の2.5% |
|
厚生労働省が8月1日に発表した2025年6月の有効求人倍率(季節調整値)は、1.22倍で、前月から0.02ポイント低下しました。 2カ月連続の低下で、3年4カ月ぶりの低水準となりました。 有効求人数が前月に比べて1.2%減少した一方で、有効求職者数は0.4%の増加となりました。 同日に総務省が発表した労働力調査によると、2025年6月の完全失業率(季節調整値)は2.5%で、前月からは横ばいでした。 完全失業者数は前月から変わらず172万人、就業者数は5万人減少して6832万人でした。 |
|
■ JR東日本が第1四半期決算を発表 4期連続増収増益 |
|
JR東日本は7月31日に、2026年3月期の第1四半期決算を発表しました。 これによると、連結・単体ともに5期連続で増収増益となりました。 セグメント別では、「流通・サービス事業」がエキナカ店舗の売り上げ増加などにより増収増益となりました。 「運輸事業」が、鉄道運輸収入が増加した一方で物件費の増加などにより増収減益となったのをはじめ、「不動産・ホテル事業」「その他」のいずれも増収減益となりました。 2025年度通期の業績予想は、今年4月に公表した内容を据え置きました。 JR東日本第1四半期決算 (単体) ● 営業収益 5,296億円 (対前年104.5%) ● 営業利益 989億円 (対前年 98.5%) ● 経常利益 1,043億円 (対前年104.4%) ● 四半期純利益 940億円 (対前年129.6%) |
|
■ 景気判断は「緩やかに回復している」に表現を変更し据え置き ~7月の月例経済報告~ |
|
政府は7月29日に2025年7月の月例経済報告を発表しました。 これによると景気の総括判断は、「緩やかに回復しているが、米国の通商政策等による不透明感が見られる」から「米国の通商政策による影響が一部見られるものの、緩やかに回復している」として表現を変更しました。 一方で海外経済は、「持ち直しが緩やかになっており、一部の地域において足踏みが見られるほか、関税率引き上げに伴う駆け込み需要やその反動の影響、不透明感がみられる」として据え置きました。 項目別では、「輸出」を「このところ持ち直しの動きが見られる」から「おおむね横ばいとなっている」として下方修正しました。 一方で「輸入」は「持ち直しの動きが見られる」として据え置きました。 「個人消費」は「消費者マインドが弱含んでいるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きが見られる」から、「消費者マインドの改善に遅れがみられるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きが見られる」として表現を変更しました。 「国内企業物価」も「緩やかに上昇している」から「このところ上昇テンポが鈍化している」に表現を見直しました。 先行きについては「米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクが高まっている」としていた表現を「下振れリスクには留意が必要」と表現を和らげました。 |
|
■ 消費者物価指数は46カ月連続でプラス コメ類は上昇幅が縮小 |
|
総務省は7月18日に2025年6月の全国消費者物価指数を発表しました。 これによると、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は111.4で、前年同月比で3.3%上昇しました。 消費者物価指数のプラスは46カ月連続で、伸び率は7カ月連続で3.0%を上回りました。 生鮮食品を除く食料は7.7%から8.2%に上昇幅が拡大、上昇は11カ月連続となりました。コメ類は前年同月比100.2%の上昇で、過去最大の上昇幅となった前月の101.7%を下回りました。 このほか、チョコレートは39.2%、コーヒー豆が40.2%上昇するなどしました。 エネルギー価格は2.9%上昇し、前月の8.1%上昇を下回りました。ガソリン価格が1.8%下落とマイナスに転じたほか、電気代は5.5%上昇、都市ガス代は2.8%上昇と、いずれも前月から伸びが縮小しました。 指数の対象となる522品目のうち417品目で上昇、69品目が下落しました。 |
|
■ 最低賃金の引き上げに向けて中央最低賃金審議会が議論をスタート |
|
厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会は、7月11日に最低賃金の改定目安額の議論を始めました。 中央審議会は労使の代表者などが数回にわたり協議を行い、経済情勢などを考慮して都道府県ごとの改定の目安を答申、それを参考にして各都道府県の地方審議会が話し合い、8月ごろに実際の改定額を決定し、10月以降に順次適用されます。 審議会には福岡厚労相の代わりに鰐淵副大臣が出席し、政府目標に配慮して改定額の目安を決めるよう要請しました。 物価上昇が続く中で政府は「20年代に1500円」との目標を掲げていて、今年の改定で全都道府県が1000円、平均で1100円台に達する可能性もあります。 7月の下旬にも中央審議会としての目安額をまとめる予定です。 |
|
■ 7月のさくらレポート 9地域全てで景気判断を据え置き |
|
日本銀行は7月10日に2025年7月の地域経済報告(さくらレポート)を公表しました。 各地域の景気判断について、全9地域で景気の総括判断を据え置きました。 一部に弱めの動きがみられるとしながらも、全9地域で「緩やかに回復している」「持ち直している」などと総括しました。 「関東甲信越」は「一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している」、「東北」は「持ち直している」として、それぞれ前回4月の表現を維持しました。 |
|
■ 街角景気は0.6ポイント上昇 基調判断は「回復に弱さ」に据え置き ~6月の景気ウオッチャー調査~ |
|
内閣府は7月8日に2025年6月の景気ウオッチャー調査を発表しました。 これによると6月の景気実感を示す現状判断指数(季節調整値)は前月から0.6ポイント上昇した45.0となり、2カ月連続のプラスとなりました。 指数の内訳としては、企業動向関連が前月から1.9ポイント上昇の46.1、家計動向関連が0.3ポイント上昇して44.4、となった一方、雇用動向関連は0.1ポイント低下の46.5となりました。 基調判断は、前月に下方修正した「このところ回復に弱さがみられる」で据え置きました。 先行きの判断指数は前月比1.1ポイント上昇した45.9となり2カ月連続のプラスとなりました。 夏のボーナス及び賃上げへの期待がある一方、引き続き価格上昇や米国の通商政策の影響への懸念がみられるとしています。 |
|
■ 名目賃金は41カ月連続で上昇 実質賃金は5カ月連続のマイナス 5月毎月勤労統計調査 |
|
厚生労働省は7月7日に、令和7年5月の毎月勤労統計調査(速報)を発表しました。 これによると、名目賃金に当たる現金給与総額は前年比で1.0%増の30万0141円で41カ月連続のプラスとなりました。 給与総額のうち、所定内給与は前年比2.1%増の26万8177円で、前月の2.2%増から微減となりました。 残業代などの所定外給与は1.0%増の1万9369円、賞与などの「特別に支払われた給与」は1万2595円で18.7%のマイナスとなりました。 物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金は前年比2.9%減となり5カ月連続でマイナスとなりました。 |
|
■ 一致指数2カ月ぶりのマイナス 基調判断は「悪化を示している」に下方修正 ~5月の景気動向指数~ |
|
内閣府は7月7日に2025年5月の景気動向指数の速報値を発表しました。 これによると景気の現状を示す一致指数は前月比0.1ポイント低下し、115.9となりました。 一致指数の低下は2カ月ぶりです。 投資財出荷指数などが改善した一方で、有効求人倍率や鉱工業用生産財出荷指数の悪化が指数を押し下げました。 一致指数の動きをベースに機械的に定義される基調判断は「悪化を示している」として、前月から下方修正しました。 数カ月先の景気を示す先行指数は1.1ポイント上昇の105.3と、4カ月ぶりに改善しました。 |
|
■ 景況感は2期ぶりに1ポイント改善 先行きは悪化を見込む ~日銀6月短観~ |
|
日本銀行は7月1日に2025年6月の企業短期経済観測調査(短観)を発表しました。 これによると大企業製造業の景況感を示す業況判断指数(DI)はプラス13で、前回・3月から1ポイント改善しました。 業種別では「鉄鋼」が前回から15ポイント、「紙・パルプ」が同じく11ペイントの改善となった一方で、「自動車」が5ポイントの低下となりました。 大企業非製造業の業況判断DIはプラス34で1ポイント低下し、2期ぶりに悪化しました。 業種別では「建設」「情報サービス」が5ポイントの改善となった一方で、「小売り」は3ポイントの低下となりました。 3カ月後の景況感を予測した先行き判断DIでは、大企業・製造業が1ポイント低下の3プラス12、大企業・非製造業は7ポイント低下のプラス27を見込んでいます。 |
|
■ 5月の求人倍率は前月と0.02ポイント低下の1.24倍、失業率は3カ月連続の2.5% |
|
厚生労働省が6月27日に発表した2025年5月の有効求人倍率(季節調整値)は、1.24倍で、前月から0.02ポイント低下しました。 有効求人数が前月に比べて0.3%増加した一方で、有効求職者数も1.5%の増加となりました。 物価高騰による先行き不安などから求職活動を行う動きが表れているとしています。 同日に総務省が発表した労働力調査によると、2025年5月の完全失業率(季節調整値)は2.5%で、前月からは横ばいでした。 完全失業者数は前月から4万人減少して172万人、就業者数は33万人増加して6837万人でした。 |
|
■ 消費者物価指数は45カ月連続でプラス コメ類は8カ月連続で過去最大の上昇幅を更新 |
|
総務省は6月20日に2025年5月の全国消費者物価指数を発表しました。 これによると、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は111.4で、前年同月比で3.7%上昇しました。 消費者物価指数のプラスは45カ月連続で、伸び率は6カ月連続で3.0%を上回りました。 生鮮食品を除く食料は7.0%から7.7%に上昇幅が拡大、上昇は10カ月連続となりました。コメ類は前年同月比101.7%の上昇で、8カ月連続で過去最大の上昇幅となりました。 米類は単一銘柄米のみが調査対象のため、多くがブレンド米として販売されている政府による備蓄米放出の効果は反映されていません。 指数の対象となる522品目のうち421品目で上昇、64品目が下落しました。 |
|
■ 景気判断は「米国の通商政策等による不透明感」で据え置き ~6月の月例経済報告~ |
|
政府は6月11日に2025年6月の月例経済報告を発表しました。 これによると景気の総括判断は、「緩やかに回復しているが、米国の通商政策等による不透明感が見られる」として据え置きました。 一方で海外経済は、「持ち直しが緩やかになっており、一部の地域において足踏みが見られるほか、米国の通商政策による不透明感が見られる」から「持ち直しが緩やかになっており、一部の地域において足踏みが見られるほか、関税率引き上げに伴う駆け込み需要やその反動の影響、不透明感がみられる」として表現を変更しました。 項目別では、「企業収益」について、「改善している」から「改善しているが、通商問題が及ぼす影響等に留意する必要がある」として表現を変更しました。 「個人消費」は「消費者マインドが弱含んでいるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きが見られる」、「設備投資」は「持ち直しの動きが見られる」として据え置きました。 「輸入」は「このところ持ち直しの動きが見られる」、「輸出」も「このところ持ち直しの動きが見られる」など、いずれも据え置きました。 先行きについては「雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待される」とする一方で、「米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクが高まっている」としたほか、物価上昇の継続が個人消費に及ぼす影響なども、景気を下押しするリスクとなっているとしました。 |
|
■ 街角景気は1.8ポイント上昇 基調判断は「回復に弱さ」に据え置き ~5月の景気ウオッチャー調査~ |
|
内閣府は6月9日に2025年5月の景気ウオッチャー調査を発表しました。 これによると5月の景気実感を示す現状判断指数(季節調整値)は前月から1.8ポイント上昇した44.4となり、5カ月ぶりにプラスとなりました。 指数の内訳としては、企業動向関連が前月から1.0ポイント低下の44.2となった一方で、家計動向関連が2.5ポイント上昇して44.1、雇用動向関連も2.5ポイント上昇の46.6となりました。 基調判断は、前月に下方修正した「このところ回復に弱さがみられる」で据え置きました。 先行きの判断指数は前月比2.1ポイント上昇した44.8となり6カ月ぶりにプラスとなりました。 夏のボーナスおよび賃上げへの期待がある一方、引き続き価格上昇や米国の通商政策の影響への懸念がみられるとしています。 |
|
■ 一致指数2カ月連続のマイナス 基調判断は「下げ止まり」に据え置き ~4月の景気動向指数~ |
|
内閣府は6月6日に2025年4月の景気動向指数の速報値を発表しました。 これによると景気の現状を示す一致指数は前月比0.3ポイント低下し、115.5となりました。 一致指数の低下は2カ月連続です。 投資財出荷指数や輸出数量指数、生産指数などが指数を押し下げました。 一致指数の動きをベースに機械的に定義される基調判断は「下げ止まりを示している」として、昨年5月以来の表現を据え置きました。 数カ月先の景気を示す先行指数は4.2ポイント低下の103.4と、3カ月連続でマイナスとなりました。 |
|
■ 名目賃金は40カ月連続で上昇 実質賃金は4カ月連続のマイナス 4月毎月勤労統計調査 |
|
厚生労働省は6月5日に、令和7年4月の毎月勤労統計調査(速報)を発表しました。 これによると、名目賃金に当たる現金給与総額は前年比で2.3%増の30万2453円で40カ月連続のプラスとなりました。 給与総額のうち、所定内給与は前年比2.2%増の26万9325円で、前月の1.4%増から拡大しました。 残業代などの所定外給与は0.8%増の2万226円、賞与などの「特別に支払われた給与」は1万2902円で4.1%のプラスとなりました。 物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金は前年比1.8%減となり4カ月連続でマイナスとなりました。 |
|
■ 4月の求人倍率は前月と同水準の1.26倍、失業率も横ばいの2.5% |
|
厚生労働省が5月30日に発表した2025年4月の有効求人倍率(季節調整値)は、1.26倍で、前月と同水準となりました。 有効求人数が前月に比べて0.3%増加した一方で、有効求職者数も0.2%の増加となりました。 物価高騰による先行き不安などから求職活動を始めたり、ダブルワークの職を探したりする動きが表れているとしています。 同日に総務省が発表した労働力調査によると、2025年4月の完全失業率(季節調整値)は2.5%で、前月からは横ばいでした。 完全失業者数は前月から3万人増加して176万人、就業者数は4万人減少して6804万人でした。 |
|
■ 消費者物価指数は44カ月連続でプラス コメ類が71年以来の上昇幅を更新 |
|
総務省は5月23日に2025年4月の全国消費者物価指数を発表しました。 これによると、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は110.9で、前年同月比で3.5%上昇しました。 消費者物価指数のプラスは44カ月連続で、伸び率は5カ月連続で3.0%を上回りました。 電気代が前月の8.7%上昇から13.5%上昇に、都市ガス代は2.0%から4.7%の上昇と、それぞれ上昇率が前月を大幅に上回り、エネルギー価格の上昇幅は6.6%から9.3%へ拡大しました。 生鮮食品を除く食料は6.2%から7.0%に上昇幅が拡大、コメ類は前年同月比98.4%の上昇となり、1971年1月以降で最大の上昇幅となりました。 指数の対象となる522品目のうち416品目で上昇、70品目が下落しました。 |
|
■ 景気判断は「米国の通商政策等による不透明感」で据え置き ~5月の月例経済報告~ |
|
政府は5月22日に2025年5月の月例経済報告を発表しました。 これによると景気の総括判断は、「緩やかに回復しているが、米国の通商政策等による不透明感が見られる」として据え置きました。 一方で海外経済は、「持ち直しているが、一部の地域において足踏みが見られるほか、米国の通商政策等による不透明感が見られる」から「持ち直しが緩やかになっており、一部の地域において足踏みが見られるほか、米国の通商政策による不透明感が見られる」として下方修正しました。 項目別では、「輸入」について、「おおむね横ばいとなっている」から「このところ持ち直しの動きが見られる」に情報修正しました。 一方で「輸出」については「このところ持ち直しの動きが見られる」として据え置きました。 「個人消費」は「消費者マインドが弱含んでいるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きが見られる」、「設備投資」は「持ち直しの動きが見られる」として据え置きました。 先行きについては「米通商政策の影響による景気の下振れリスクが高まっている」としました。 |
|
■ 街角景気は2.5ポイント低下 基調判断は「回復に弱さ」に下方修正 ~4月の景気ウオッチャー調査~ |
|
内閣府は5月12日に2025年4月の景気ウオッチャー調査を発表しました。 これによると4月の景気実感を示す現状判断指数(季節調整値)は前月から2.5ポイント低下の42.6となり、4カ月連続でマイナスとなりました。 コロナ禍により景況感が悪化していた2022年2月の37.4以来の低水準となりました。 指数の内訳としては、家計動向関連が前月から2.8ポイント低下して41.6、企業動向関連は1.7ポイント低下の45.2、雇用動向関連も1.9ポイント低下の44.1で、3部門すべてでマイナスとなりました。 基調判断は、「緩やかな回復基調が続いているものの、このところ弱さがみられる」から「このところ回復に弱さがみられる」に下方修正しました。 先行きの判断指数は前月比2.5ポイント低下した42.7で5カ月連続のマイナスとなりました。 賃上げへの期待がある一方、従前からみられる価格上昇の影響に加え、米国の通商政策の影響への懸念が強まっているとしています。 |
|
■ 名目賃金は39カ月連続で上昇 実質賃金は3カ月連続のマイナス 3月毎月勤労統計調査 |
|
厚生労働省は5月9日に、令和7年3月の毎月勤労統計調査(速報)を発表しました。 これによると、名目賃金に当たる現金給与総額は前年比で2.1%増の30万8572円で39カ月連続のプラスとなりました。 給与総額のうち、所定内給与は前年比1.3%増の26万2896円で、前月の1.6%増から減速しました。 残業代などの所定外給与は1.1%減の1万9683円、賞与などの「特別に支払われた給与」は2万5993円で13.9%のプラスとなりました。 物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金は前年比2.1%減となり3カ月連続でマイナスとなりました。 名目賃金の伸びが物価上昇に届かなかったことで、実質賃金は減少しました。 |
|
■ 一致指数4カ月ぶりのマイナス 基調判断は「下げ止まり」に据え置き ~3月の景気動向指数~ |
|
内閣府は5月9日に2025年3月の景気動向指数の速報値を発表しました。 これによると景気の現状を示す一致指数は前月比1.3ポイント低下し、116.0となりました。 一致指数の低下は4カ月ぶりです。 耐久財や鉱工業用生産財の出荷指数、投資財出荷指数や輸出数量指数などが指数を押し下げました。 一致指数の動きをベースに機械的に定義される基調判断は「下げ止まりを示している」として、昨年5月以来の表現を据え置きました。 数カ月先の景気を示す先行指数は0.5ポイント低下の107.7と、2カ月連続でマイナスとなりました。 |
|
■ 3月の求人倍率は0.02ポイント上昇の1.26倍、失業率は0.1ポイント悪化の2.5%に |
|
厚生労働省が5月2日に発表した2025年3月の有効求人倍率(季節調整値)は、1.26倍で、前月から0.02ポイント上昇しました。 有効求人数が前月に比べて0.3%増加した一方で、有効求職者数は1.2%の減少となりました。 現在の職場での賃上げへの期待や、物価高による先行き不安などから、転職活動に慎重な傾向が表れているとしています。 同日に総務省が発表した労働力調査によると、2025年3月の完全失業率(季節調整値)は2.5%と0.1ポイント上昇し、6カ月ぶりに悪化しました。 完全失業者数は前月から5万人増加して173万人、就業者数は8万人減少して6808万人でした。 |
|
■ JR東日本が2024年度期末決算を発表 すべてのセグメントで増収増益 |
|
JR東日本は4月30日に、2024年度の期末決算を発表しました。 これによると、連結・単体ともに4期連続で増収増益となりました。 連結の営業収益は対前年比105.8%の2兆8875億円、経常利益は同108.4%の3215億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同114.2%の2242億円でいずれも計画を上回りました。 単体でも営業収益は対前年比104.5%の2兆0776億円、経常利益は同107.0%の2165億円、当期純利益は同104.0%の1526億円でした。 セグメント別では、鉄道運輸収入が増加したことなどにより運輸事業が増収増益となったのをはじめ、流通・サービス事業、不動産・ホテル事業、その他のすべてのセグメントで増収増益となりました。 JR東日本期末決算 (単体) ● 営業収益 20,776億円 (対前年104.5%) ● 営業利益 2,660億円 (対前年104.8%) ● 経常利益 2,165億円 (対前年107.0%) ● 当期純利益 1,526億円 (対前年104.0%) |
|
■ 景気判断は「米国の通商政策等による不透明感」へ表現変更 ~4月の月例経済報告~ |
|
政府は4月18日に2025年4月の月例経済報告を発表しました。 これによると景気の総括判断は、前月までの「一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している」を「緩やかに回復しているが、米国の通商政策等による不透明感が見られる」へ表現を改めました。 海外経済も「一部の地域において足踏みが見られるものの、持ち直している」から「持ち直しているが、一部の地域において足踏みが見られるほか、米国の通商政策等による不透明感が見られる」として表現を改めました。 いずれもアメリカの関税政策に対する警戒を強めた内容となりました。 項目別では、「業況判断」について、「改善している」から「このところおおむね横ばいとなっている」に下方修正しました。 「個人消費」は「一部に足踏みが残るものの、このところ持ち直しの動きが見られる」から、「消費者マインドが弱含んでいるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きが見られる」として表現を変更しました。 |
|
■ 消費者物価指数は43カ月連続でプラス コメ類が71年以来の上昇幅を更新 |
|
総務省は4月18日に2025年3月の全国消費者物価指数を発表しました。 これによると、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は110.2で、前年同月比で3.2%上昇しました。 消費者物価指数のプラスは43カ月連続で、伸び率は4カ月連続で3.0%を上回りました。 電気代が前月の9.0%から8.7%上昇、都市ガス代は3.5%から2.0%の上昇と、それぞれ上昇率が前月を下回り、エネルギー価格の上昇幅は6.9%から6.6%へ縮小しました。 生鮮食品を除く食料は5.6%から6.2%に上昇幅が拡大、コメ類は前年同月比92.1%の上昇となり、1971年1月以降で最大の上昇幅となりました。 指数の対象となる522品目のうち414品目で上昇、73品目が下落しました。 |
|
■ 街角景気は0.5ポイント低下 基調判断は「このところ弱さ」で横ばい ~3月の景気ウオッチャー調査~ |
|
内閣府は4月8日に2025年3月の景気ウオッチャー調査を発表しました。 これによると3月の景気実感を示す現状判断指数(季節調整値)は前月から0.5ポイント低下の45.1となり、3カ月連続でマイナスとなりました。 指数の内訳としては、家計動向関連が前月から0.1ポイント低下して44.4、企業動向関連は0.5ポイント低下の46.9、雇用動向関連も3.9ポイント低下の46.0で、3部門すべてでマイナスとなりました。 基調判断は、「緩やかな回復基調が続いているものの、このところ弱さがみられる」を維持しました。 先行きの判断指数は前月比1.4ポイント低下した45.2で4カ月連続のマイナスとなりました。 |
|
■ 4月のさくらレポート 9地域全てで景気判断を据え置き |
|
日本銀行は4月7日に2025年4月の地域経済報告(さくらレポート)を公表しました。 各地域の景気判断について、全9地域で景気の総括判断を据え置きました。 アメリカの関税政策を念頭に、経済を巡る不確実性が高まっている現状を反映しました。 「関東甲信越」は「一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している」、「東北」は「緩やかに持ち直している」として、それぞれ前回1月の表現を維持しました。 |
|
■ 名目賃金は38カ月連続で上昇 実質賃金は2カ月連続のマイナス 2月毎月勤労統計調査 |
|
厚生労働省は4月7日に、令和7年2月の毎月勤労統計調査(速報)を発表しました。 これによると、名目賃金に当たる現金給与総額は前年比で3.1%増の28万9562円で38カ月連続のプラスとなりました。 給与総額のうち、所定内給与は前年比1.6%増の26万1498円で、前月の2.1%増から減速しました。 残業代などの所定外給与は2.2%増の1万9447円で5カ月連続のプラス、賞与などの「特別に支払われた給与」は8617円で少額ながら、前年が少なかったため77.4%と大幅なプラスとなりました。 物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金は前年比1.2%減となり2カ月連続でマイナスとなりました。 名目賃金の伸びが物価の上昇に届かなかったことで、実質賃金は減少しました。 |
|
■ 一致指数3カ月連続のプラス 基調判断は「下げ止まり」に据え置き ~2月の景気動向指数~ |
|
内閣府は4月7日に2025年2月の景気動向指数の速報値を発表しました。 これによると景気の現状を示す一致指数は前月比0.8ポイント上昇し、116.9となりました。 一致指数の上昇は3カ月連続です。 投資財出荷指数や鉱工業生産指数などが指数を押し上げました。 一致指数の動きをベースに機械的に定義される基調判断は「下げ止まりを示している」として、昨年5月以来の表現を据え置きました。 数カ月先の景気を示す先行指数は0.3ポイント低下の107.9と、3カ月ぶりにマイナスに転じました。 |
|
■ 景況感は前回から2ポイント悪化 先行きも悪化を見込む ~日銀3月短観~ |
|
日本銀行は4月1日に2025年3月の企業短期経済観測調査(短観)を発表しました。 これによると大企業製造業の景況感を示す業況判断指数(DI)はプラス12で、前回・12月から2ポイント悪化しました。 業種別では「自動車」がプラス13と前回から5ポイントの改善となった一方で、「鉄鋼」が前回のマイナス8からマイナス18、「繊維」がプラス23から0など、大きく悪化しました。 大企業非製造業の業況判断DIはプラス35で2ポイント上昇し、2期ぶりに改善しました。 業種別では「宿泊・飲食サービス」がプラス46と前回から6ポイントの改善となったほか、「小売り」も前回のプラス13からプラス21となり大きく改善しました。 3カ月後の景況感を予測した先行き判断DIでは、大企業・製造業が3ポイント低下のマイナス1、大企業・非製造業は7ポイント低下のプラス9を見込んでいます。 |
|
■ 2月の求人倍率は0.02ポイント低下の1.24倍、失業率は0.1ポイント低下の2.4%に |
|
厚生労働省が4月1日に発表した2025年2月の有効求人倍率(季節調整値)は、1.24倍で、前月から0.02ポイント低下しました。 有効求人数が前月に比べて1.7%減少、有効求職者数も0.5%の減少となりました。 賃上げなど労働条件の改善を背景に、現在の職場からの離転職を踏みとどまる動きが継続しているとしています。 同日に総務省が発表した労働力調査によると、2025年2月の完全失業率(季節調整値)は2.4%と0.1ポイント低下し、5カ月ぶりに改善しました。 完全失業者数は前月から6万人減少して168万人、就業者数も11万人減少して6816万人でした。 |
|
■ 消費者物価指数は42カ月連続でプラス コメ類が71年以来の上昇幅を更新 |
|
総務省は3月21日に2025年2月の全国消費者物価指数を発表しました。 これによると、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は109.7で、前年同月比で3.0%上昇しました。 消費者物価指数のプラスは42カ月連続で、伸び率は3カ月連続で3.0%を上回りました。 電気代が前月の18.0%から9.0%上昇、都市ガス代は9.6%から3.5%の上昇と、それぞれ上昇率が前月を大幅に下回った一方で、ガソリンが3.9%から5.8%に上昇し、エネルギー価格は10.8%から6.9%へ縮小しました。 生鮮食品を除く食料は5.1%から5.6%に上昇幅が拡大、コメ類は前年同月比80.9%の上昇となり、1971年1月以降で最大の上昇幅となりました。 指数の対象となる522品目のうち405品目で上昇、77品目が下落しました。 |
|
■ 景気判断は「一部足踏みも緩やかに回復」で据え置き ~3月の月例経済報告~ |
|
政府は3月19日に2025年3月の月例経済報告を発表しました。 これによると景気の総括判断は、「一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している」として据え置きました。 海外経済も「一部の地域において足踏みが見られるものの、持ち直している」で据え置きました。 項目別では、「企業収益」について、「総じて見れば改善している」から「改善している」に上方修正しました。 前月に11カ月ぶりに下方修正した「輸入」は「おおむね横ばいとなっている」として据え置きました。 その他の項目もすべて据え置きとし、「個人消費」は「一部に足踏みが残るものの、このところ持ち直しの動きが見られる」、「設備投資」は「持ち直しの動きが見られる」などとしました。 先行きについては注意する要因として「米国の政策動向による影響などがわが国の景気を下押しするリスクとなっている」としました。 |
|
■ 街角景気は3.0ポイント低下 基調判断は「このところ弱さ」に下方修正 ~2月の景気ウオッチャー調査~ |
|
内閣府は3月10日に2025年2月の景気ウオッチャー調査を発表しました。 これによると2月の景気実感を示す現状判断指数(季節調整値)は前月から3.0ポイント低下の45.6となり、2カ月連続でマイナスとなりました。 指数の内訳としては、雇用動向関連が2.0ポイント上昇して49.9になった一方で、企業動向関連は1.5ポイント低下の47.4、家計動向関連が前月から4.1ポイント低下の44.5となりました。 基調判断は、「緩やかな回復基調が続いているものの、このところ弱さがみられる」として、10カ月ぶりに下方修正しました。 先行きの判断指数は前月比1.4ポイント低下した46.6で3カ月連続のマイナスとなりました。 |
|
■ 名目賃金は37カ月連続で上昇 実質賃金は3カ月ぶりのマイナス 1月毎月勤労統計調査 |
|
厚生労働省は3月10日に、令和7年1月の毎月勤労統計調査(速報)を発表しました。 これによると、名目賃金に当たる現金給与総額は前年比で2.8%増の29万5505円で37カ月連続のプラスとなりました。 給与総額のうち、所定内給与は前年比3.1%増の26万3710円で、32年3カ月ぶりの高い伸び率を記録しました。 残業代などの所定外給与は3.1%増の1万9478円で4カ月連続のプラス、賞与などの「特別に支払われた給与」は3.7%減の1万2317円で3カ月ぶりのマイナスでした。 物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金は前年比1.8%減で3カ月ぶりにマイナスとなりました。 名目賃金の伸びを物価の上昇が大きく上回ったことで、実質賃金は減少しました。 |
|
■ 一致指数2カ月連続のプラス 基調判断は「下げ止まり」に据え置き ~1月の景気動向指数~ |
|
内閣府は3月10日に2025年1月の景気動向指数の速報値を発表しました。 これによると景気の現状を示す一致指数は前月比0.1ポイント上昇し、116.2となりました。 一致指数の上昇は2カ月連続です。 耐久財消費財出荷や卸売・小売販売額、有効求人倍率などが指数を押し上げました。 一致指数の動きをベースに機械的に定義される基調判断は「下げ止まりを示している」として、昨年5月以来の表現を据え置きました。 数カ月先の景気を示す先行指数は0.1ポイント上昇の108.0と、2カ月連続のプラスでした。 |
|
■ 1月の求人倍率は0.01ポイント上昇の1.26倍、失業率は横ばいの2.5%に |
|
厚生労働省が3月4日に発表した2025年1月の有効求人倍率(季節調整値)は、1.26倍で、前月から0.01ポイント上昇しました。 有効求人数が前月に比べて0.2%増加した一方で、有効求職者数は0.3%の減少となりました。 賃上げの機運を背景に、現在の職場からの離転職を踏みとどまる動きが継続しているとしています。 同日に総務省が発表した労働力調査によると、2025年1月の完全失業率(季節調整値)は2.5%で前月から横ばいでした。 完全失業者数は前月から2万人増加して174万人、就業者数も13万人増加して6827万人でした。 |
|
■ 消費者物価指数は41カ月連続でプラス コメ類が71年以来の上昇幅 |
|
総務省は2月21日に2025年1月の全国消費者物価指数を発表しました。 これによると、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は109.8で、前年同月比で3.2%上昇しました。 消費者物価指数のプラスは41カ月連続で、伸び率は前月の3.0%を上回り、1年7カ月ぶりの水準にとなりました。 電気代が前月の18.7%から18.0%、都市ガス代は11.1%から9.6%と上昇率が前月を下回った一方で、ガソリンが0.7%から3.9%に上昇し、エネルギー価格は10.1%から10.8%へ上昇しました。 生鮮食品を除く食料は4.4%から5.1%に上昇幅が拡大、コメ類は前年同月比70.9%上昇し、1971年1月以降で最大の上昇幅となりました。 生鮮野菜は36.0%の上昇、生鮮食品は前月の17.3%から21.9%に伸び率が拡大しました。 指数の対象となる522品目のうち398品目で上昇、84品目が下落しました。 |
|
■ 景気判断は「一部足踏みも緩やかに回復」で据え置き ~2月の月例経済報告~ |
|
政府は2月19日に2025年2月の月例経済報告を発表しました。 これによると景気の総括判断は、「一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している」として据え置きました。 海外経済も「一部の地域において足踏みが見られるものの、持ち直している」で据え置きました。 項目別では、「輸出」について「おおむね横ばいとなっている」から「このところ持ち直しの動きが見られる」に上方修正しました。上方修正は2023年8月以来18カ月ぶりです。 一方で「輸入」は「このところ持ち直しの動きがみられる」から「おおむね横ばいとなっている」として下方修正しました。下方修正は2024年3月以来11カ月ぶりです。 その他の項目はすべて据え置きとし、「個人消費」は「一部に足踏みが残るものの、このところ持ち直しの動きが見られる」、「設備投資」は「持ち直しの動きが見られる」などとしました。 先行きについては注意する要因として米国の政策動向に「通商政策」を加え、海外景気の下振れリスクに「十分注意する必要」があるとしました。 |
|
■ 街角景気は0.4ポイント低下 基調判断は「緩やかな回復」を維持 ~1月の景気ウオッチャー調査~ |
|
内閣府は2月10日に2025年1月の景気ウオッチャー調査を発表しました。 これによると1月の景気実感を示す現状判断指数(季節調整値)は前月から0.4ポイント低下の48.6となり、3カ月ぶりでマイナスとなりました。 指数の内訳としては企業動向関連も0.3ポイント上昇の48.9となった一方で、家計動向関連が前月から0.6ポイント低下の48.6、雇用動向関連が0.7ポイント低下して47.9となりました。 基調判断は、「緩やかな回復基調が続いている」を維持しました。 先行きの判断指数は前月比1.4ポイント低下した48.0で2カ月連続のマイナスとなました。 |
|
■ 一致指数2カ月ぶりのプラス 基調判断は「下げ止まり」に据え置き ~12月の景気動向指数~ |
|
内閣府は2月7日に2024年12月の景気動向指数の速報値を発表しました。 これによると景気の現状を示す一致指数は前月比1.4ポイント上昇し、116.8となりました。 一致指数の上昇は2カ月ぶりです。 輸出数量指数や投資財出荷指数、小売販売額の改善などが指数を押し上げました。 一致指数の動きをベースに機械的に定義される基調判断は「下げ止まりを示している」として、昨年5月以来の表現を据え置きました。 数カ月先の景気を示す先行指数は1.1ポイント上昇の108.9と、2カ月ぶりに上昇しました。 |
|
■ 名目賃金は36カ月連続で上昇 実質賃金は2カ月連続のプラス 12月毎月勤労統計調査 |
|
厚生労働省は2月5日に、2024年12月の毎月勤労統計調査(速報)を発表しました。 これによると、名目賃金に当たる現金給与総額は前年比で4.8%増の61万9580円で36カ月連続のプラスとなりました。 給与総額のうち、所定内給与は前年比2.7%増の26万5303円でした。 残業代などの所定外給与は1.3%増の2万0359円で3カ月連続のプラス、賞与などの「特別に支払われた給与」は6.9%増の33万3918円で2カ月連続のプラスでした。 物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金は前年比0.6%増で2カ月連続のプラスとなりました。 2024年通年では、実質賃金は0.2%減少して3年連続のマイナスでした。 |
|
■ JR東日本が第3四半期決算を発表 4期連続の増収増益 |
|
JR東日本は2月3日に、2025年3月期の第3四半期決算を発表しました。 これによると、連結・単体ともに4期連続で増収増益となりました。 <p> 連結の営業収益は対前年6.2%増の2兆1260億円、本業の儲けを示す営業利益が同18.1%増の3525億となったのをはじめ、全ての利益が増益でした。 セグメント別では、「運輸事業」が鉄道運輸収入の増加などにより増収増益となったのをはじめ、「流通・サービス事業」「不動産・ホテル事業」で増収増益となりました。 一方で「その他」は、エネルギー事業関連の費用計上などにより、増収減益となりました。 2024年度通期の業績予想は、昨年4月に公表した内容を据え置きました。 JR東日本第3四半期決算 (単体) ● 営業収益 15,524億円 (対前年106.5%) ● 営業利益 2,812億円 (対前年122.4%) ● 経常利益 2.475億円 (対前年130.3%) ● 四半期純利益 1,798億円 (対前年129.2%) |
|
■ 12月の求人倍率は横ばいの1.25倍、失業率は2.4%に改善 |
|
厚生労働省が1月31日に発表した2024年12月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月と変わらず1.25倍でした。 有効求人数は前月に比べて0.2%減少、有効求職者数も0.2%の減少となりました。 賃上げの機運を背景に、現在の職場からの離転職を踏みとどまる動きがあるとしています。 同日に総務省が発表した労働力調査によると、2024年12月の完全失業率(季節調整値)は2.4%で前月から0.1ポイント改善しました。 完全失業者数は前月から2万人減少して170万人、就業者数も14万人増加して6822万人でした。 |
|
■ 消費者物価指数は40カ月連続でプラス エネルギー関連が大幅に上昇 |
|
総務省は1月24日に2024年12月の全国消費者物価指数を発表しました。 これによると、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は109.6で、前年同月比で3.0%上昇しました。 消費者物価指数のプラスは40カ月連続で、伸び率は前月の2.7%を上回り、1年4カ月ぶりの水準にとなりました。 政府の補助金が終了したことで電気代が前月の9.9%から18.7%、都市ガス代は6.4%から11.1%とともに前月を大幅に上回り、エネルギー価格は6.0%から10.1%への大幅に上昇しました。 生鮮食品を除く食料は3・8%上昇、コシヒカリを除くうるち米が前年比65.5%上昇と高い伸びとなりました。 2024年通年のコアCPIも同時に公表され、前年比2.5%上昇と3年連続のプラスとなりました。伸びは2023年の3.1%から縮小しました。 |
|
■ 景気判断は「一部足踏みも緩やかに回復」で据え置き ~1月の月例経済報告~ |
|
政府は1月23日に2025年1月の月例経済報告を発表しました。 これによると景気の総括判断は、「一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している」として据え置きました。 海外経済も「一部の地域において足踏みが見られるものの、持ち直している」で据え置きました。 項目別では、「倒産件数」について「おおむね横ばいとなっている」に上方修正しました。上方修正は昨年9月以来4カ月ぶりです。 その他の項目はすべて据え置きとし、「個人消費」は「一部に足踏みが残るものの、このところ持ち直しの動きが見られる」、「設備投資」は「持ち直しの動きが見られる」などとしました。 先行きについては前月と同様に、緩やかな回復が続くと期待されるとする一方で、物価高や米国の政策動向、中東地域を巡る情勢などの影響に十分注意する必要があるとしました。 |
|
■ 街角景気は0.5ポイント上昇 基調判断は「緩やかな回復」を維持 ~12月の景気ウオッチャー調査~ |
|
内閣府は1月14日に2024年12月の景気ウオッチャー調査を発表しました。 これによると12月の景気実感を示す現状判断指数(季節調整値)は前月から0.5ポイント上昇の49.9となり、2カ月連続でプラスとなりました。 指数の内訳としては家計動向関連が前月から0.6ポイント上昇の50.2、企業動向関連も0.6ポイント上昇の49.1となった一方で、雇用動向関連が0.2ポイント低下して49.7となりました。 基調判断は、前月に上方修正した「緩やかな回復基調が続いている」を維持しました。 先行きの判断指数は前月比0.6ポイント低下した48.8で2カ月ぶりのマイナスとなました。 |
|
■ 一致指数3カ月ぶりのマイナス 基調判断は「下げ止まり」に据え置き ~11月の景気動向指数~ |
|
内閣府は1月10日に2024年11月の景気動向指数の速報値を発表しました。 これによると景気の現状を示す一致指数は前月比1.5ポイント低下し、115.3となりました。 一致指数の低下は3カ月ぶりです。 投資財出荷指数や耐久消費財出荷指数、輸出数量指数の悪化などが指数を押し下げました。 一致指数の動きをベースに機械的に定義される基調判断は「下げ止まりを示している」として、昨年5月以来の表現を据え置きました。 数カ月先の景気を示す先行指数は2.1ポイント低下の107.3とマイナスになりました。 |
|
■ 1月のさくらレポート 北陸と東北で景気判断を引き上げ |
|
日本銀行は1月9日に2025年1月の地域経済報告(さくらレポート)を公表しました。 各地域の景気判断について、全国9地域中、北陸と東北の2地域で景気の総括判断を引き上げました。 北陸はインバウンや新幹線延伸の効果、東北は生産停止の影響からの回復が反映されました。 残る7地域では前回7月の報告から判断を据え置きしました。 「関東甲信越」は「一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している」、「東北」は「緩やかに持ち直している」として、それぞれ前回7月の表現を維持しました。 |
|
■ 名目賃金は35カ月連続で上昇 実質賃金は4カ月連続のマイナス 11月毎月勤労統計調査 |
|
厚生労働省は1月9日に、2024年11月の毎月勤労統計調査(速報)を発表しました。 これによると、名目賃金に当たる現金給与総額は前年比で3.0%増の30万5832円で35カ月連続のプラスとなりました。 給与総額のうち、所定内給与は前年比2.7%増の26万5082円でした。 残業代などの所定外給与は1.6%増の2万0659円で2カ月連続のプラス、賞与などの「特別に支払われた給与」も7.9%増の2万0091円で2カ月ぶりのプラスでした。 物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金は前年比0.3%減で4カ月連続のマイナスとなりました。 |
|
■ 11月の求人倍率は横ばいの1.25倍、失業率も2.5%で前月と変わらず |
|
厚生労働省が12月27日に発表した2024年11月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月と変わらず1.25倍でした。 有効求人数は前月に比べて0.7%増加、有効求職者数も0.6%の増となりました。 物価高や最低賃金の引き上げなどを踏まえて、より良い転職の時期を検討している人が多いとしています。 同日に総務省が発表した労働力調査によると、2024年11月の完全失業率(季節調整値)は前月から横ばいの2.5%でした。 完全失業者数は前月から1万人増加して172万人、就業者数も10万人増加して6808万人でした。 |
|
■ 景気判断は「一部足踏みも緩やかに回復」で据え置き ~12月の月例経済報告~ |
|
政府は12月20日に2024年12月の月例経済報告を発表しました。 これによると景気の総括判断は、「一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している」として据え置きました。 海外経済も「一部の地域において足踏みが見られるものの、持ち直している」で据え置きました。 項目別では、「企業収益」について「総じて見れば改善している」から「総じて見れば改善しているが、そのテンポは緩やかになっている」に下方修正しました。 「個人消費」は「一部に足踏みが残るものの、このところ持ち直しの動きが見られる」で据え置きました。 「輸入」については、「このところ持ち直しの動きが見られる」、「輸出」は「おおむね横ばいとなっている」で据え置きました。 また、「設備投資」も「持ち直しの動きが見られる」、「公共投資」も「底堅く推移している」として、いずれも据え置きました。 |
|
■ 消費者物価指数は39カ月連続でプラス 生鮮食品を除く食料は伸び率が拡大 |
|
総務省は12月20日に2024年11月の全国消費者物価指数を発表しました。 これによると、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は109.2で、前年同月比で2.7%上昇しました。 消費者物価指数のプラスは39カ月連続で、伸び率は前月の2.3%を下回り、3カ月ぶりに伸び率が拡大しました。 電気代が9.9%、都市ガス代は6.4%とともに前月を大幅に上回り、エネルギー価格は前月の2.3%上昇から6.0%上昇となり、伸び率が拡大しました。 生鮮食品を除く食料は4.2%上昇で、4カ月連続で伸び率を拡大、米価格上昇などを受けて7カ月ぶりの高い伸びとなりました。 対象522品目のうち、389品目で上昇、97品目で下落しました。 |
|
■ 景況感は小幅な改善 先行きは悪化を見込む ~日銀12月短観~ |
|
日本銀行は12月13日に2024年12月の企業短期経済観測調査(短観)を発表しました。 これによると大企業製造業の景況感を示す業況判断指数(DI)はプラス14で1ポイント上昇し、2期ぶりに改善しました。 製造業のDIは全16業種のうち7業種は悪化した一方で6業種が改善し、2022年3月以来の高水準となりました。 また、大企業非製造業の業況判断DIはプラス33で1ポイント低下し、2期ぶりに悪化しました。 3カ月後の景況感を予測した先行き判断DIでは、大企業・製造業がプラス13、大企業・非製造業はプラス28で、ともに悪化を見込んでいます。 |
|
■ 街角景気は1.9ポイント上昇 基調判断は「緩やかな回復」を維持 ~11月の景気ウオッチャー調査~ |
|
内閣府は12月9日に2024年11月の景気ウオッチャー調査を発表しました。 これによると11月の景気実感を示す現状判断指数(季節調整値)は前月から1.9ポイント上昇の49.4となり、3カ月ぶりのプラスとなりました。 指数の内訳としては家計動向関連が前月から3.2ポイント上昇の49.6となった一方で、雇用動向関連が0.3ポイント低下して49.9、企業動向関連が1.0ポイント低下の48.5となりました。 基調判断は、前月に上方修正した「緩やかな回復基調が続いている」を維持しました。 先行きの判断指数は前月比1.1ポイント上昇した49.4で3カ月ぶりのプラスとなりました。 |
|
■ 名目賃金は34カ月連続で上昇 実質賃金は横ばい 10月毎月勤労統計調査 |
|
厚生労働省は12月6日に、2024年10月の毎月勤労統計調査(速報)を発表しました。 これによると、名目賃金に当たる現金給与総額は前年比で2.6%増の29万3401円で34カ月連続のプラスとなりました。 給与総額のうち、所定内給与は前年比2.7%増の26万5537円でした。 残業代などの所定外給与は1.4%増の2万0341円で2カ月ぶりのプラス、賞与などの「特別に支払われた給与」1.7%減の7523円でした。 物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金は前年比横ばいとなりました。 |
|
■ 一致指数2カ月連続のプラス 基調判断は「下げ止まり」に据え置き ~10月の景気動向指数~ |
|
内閣府は12月6日に2024年10月の景気動向指数の速報値を発表しました。 これによると景気の現状を示す一致指数は前月比2.5ポイント上昇し、116.5となりました。 一致指数の上昇は2カ月連続です。 投資財出荷指数や鉱工業生産指数の改善などが指数を押し上げました。 一致指数の動きをベースに機械的に定義される基調判断は「下げ止まりを示している」として5月以来の表現を据え置きました。 数カ月先の景気を示す先行指数は0.3ポイント低下の108.6となり、2カ月ぶりにマイナスとなりました。 |
|
■ 10月の求人倍率は1.25倍に上昇、失業率は2.5%に悪化 |
|
厚生労働省が11月29日に発表した2024年10月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月から0.01ポイント上昇して1.25倍でした。 有効求人数は前月に比べて0.2%増加した一方で、有効求職者数は0.7%の減となりました。 コスト増加を背景に、引き続き製造業や建設業で求人を手控える傾向が見られるとしています。 同日に総務省が発表した労働力調査によると、2024年9月の完全失業率(季節調整値)は2.5%で、0.1ポイントの上昇となりました。 完全失業率の悪化は3カ月ぶりです。 完全失業者数は前月から3万人増加して171万人、就業者数も16万人増加して6798万人でした。 |
|
■ 景気判断は「一部足踏みも緩やかに回復」で据え置き ~11月の月例経済報告~ |
|
政府は11月26日に2024年11月の月例経済報告を発表しました。 これによると景気の総括判断は、「一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している」として据え置きました。 海外経済も「一部の地域において足踏みが見られるものの、持ち直している」で据え置きました。 項目別では、「輸入」について、「おおむね横ばいとなっている」から「このところ持ち直しの動きが見られる」として上方修正しました。 一方で「公共投資」は「底堅く推移している」として下方修正しました。 このほか「国内企業物価」は「このところ緩やかに上昇している」、「消費者物価」は「このところ上昇している」として表現を変更しました。 「個人消費」は「一部に足踏みが残るものの、このところ持ち直しの動きが見られる」、「設備投資」は「持ち直しの動きが見られる」としていずれも据え置きました。 |
|
■ 消費者物価指数は38カ月連続でプラス 生鮮食品を除く食料は7カ月ぶりの伸び |
|
総務省は11月22日に2024年10月の全国消費者物価指数を発表しました。 これによると、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は108.8で、前年同月比で2.3%上昇しました。 消費者物価指数のプラスは38カ月連続で、伸び率は前月の2.4%を下回り、2カ月連続で縮小しました。 エネルギー価格は2.3%上昇で前月の6.0%上昇から縮小しました。 生鮮食品を除く食料は3.8%上昇で、米価格上昇などを受けて7カ月ぶりの高い伸びとなりました。 |
|
■ 街角景気は0.3ポイント低下 基調判断は「緩やかな回復」を維持 ~10月の景気ウオッチャー調査~ |
|
内閣府は11月11日に2024年10月の景気ウオッチャー調査を発表しました。 これによると10月の景気実感を示す現状判断指数(季節調整値)は前月から0.3ポイント低下の47.5となり2カ月連続のマイナスとなりました。 指数の内訳としては家計動向関連が前月から0.6ポイント低下の46.4となった一方で、雇用動向関連が0.4ポイント上昇して50.2、企業動向関連が0.2ポイント上昇の49.5となりました。 基調判断は、前月に上方修正した「緩やかな回復基調が続いている」を維持しました。 先行きの判断指数は前月比1.4ポイント低下した48.3で2カ月連続のマイナスとなました。 |
|
■ 一致指数2カ月ぶりのプラス 基調判断は「下げ止まり」に据え置き ~9月の景気動向指数~ |
|
内閣府は11月8日に2024年9月の景気動向指数の速報値を発表しました。 これによると景気の現状を示す一致指数は前月比1.7ポイント上昇し、115.7となりました。 一致指数の上昇は2カ月ぶりです。 鉱工業用生産財出荷指数や輸出数量指数の改善などが指数を押し上げました。 一致指数の動きをベースに機械的に定義される基調判断は「下げ止まりを示している」で据え置きました。 数カ月先の景気を示す先行指数は2.5ポイント上昇の109.4となり、2カ月ぶりにプラスとなりました。 |
|
■ 名目賃金は33カ月連続で上昇 実質賃金は2カ月連続マイナスに 9月毎月勤労統計調査 |
|
厚生労働省は11月7日に、2024年9月の毎月勤労統計調査(速報)を発表しました。 これによると、名目賃金に当たる現金給与総額は前年比で2.8%増の29万2551円で33カ月連続のプラスとなりました。 給与総額のうち、所定内給与は前年比2.6%増の26万4194円でした。 残業代などの所定外給与は0.4%減の1万9164円で3カ月ぶりのマイナス、賞与などの「特別に支払われた給与」16.1%増の9193円でした。 物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金は0.1%減で、2カ月連続のマイナスとなりました。 |
|
■ JR東日本が第2四半期決算を発表 4期連続の増収増益 |
|
JR東日本は10月31日に、2025年3月期の第2四半期決算を発表しました。 これによると、連結・単体ともに4期連続で増収増益となりました。 連結の営業収益は対前年7.3%増の1兆3951億円、本業の儲けを示す営業利益は同22.8%増の2356億でした。 セグメント別では、「運輸事業」が鉄道運輸収入の増加などにより増収増益となったのをはじめ、「流通・サービス事業」「不動産・ホテル事業」で増収増益となりました。 一方で「その他」は、海外鉄道事業関連の売上が増加したもののエネルギー事業関連の費用計上などにより、増収減益となりました。 2024年度通期の業績予想は、今年4月に公表した内容を据え置きました。 JR東日本第2四半期決算 (単体) ● 営業収益 10,261億円 (対前年107.2%) ● 営業利益 1,960億円 (対前年126.4%) ● 経常利益 1,775億円 (対前年136.2%) ● 四半期純利益 1,258億円 (対前年134.5%) |