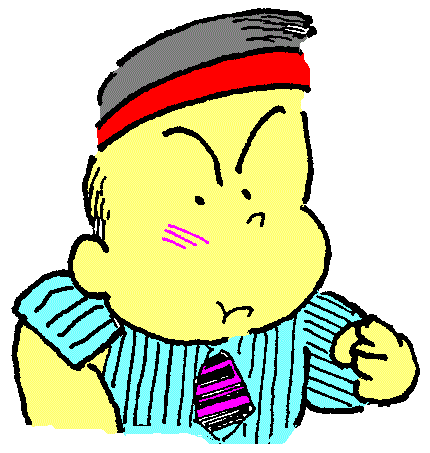 |
|
|
■ 中央執行委員会見解を発出 (2024年 3月15日) |
|
中央本部は2024年度賃金改定妥結に当たり、3月15日付で中央執行委員会見解を発出しました。 2024春闘妥結に関する中央執行委員会見解
私たち東日本ユニオンは、申第21号「2024年賃金改定に関する申し入れ」に対し、社員の基本給引き上げは要求額に迫る回答を引き出したこと。定期昇給は「昇給係数4」の満額回答、エルダー社員の基本賃金引き上げ額も満額回答を確認し「妥結」を判断しました。 経営側は3月8日の3回目となる団体交渉の席上で新賃金回答を示しました。組合側が一貫して主張した「一律」のベースアップに対して、職制に比重をおいた所定昇給額を算定基礎とする回答であることから「持ち帰り検討」を通告し、直ちに中央執行委員会で協議しました。 中央執行委員会において、ベースアップに社員間で格差をつけたことは認められないこと、あらためて社員「一律」によるベースアップを勝ちとることを課題に継続して取り組んでいくこと確認しました。 会社回答以降、格差ベアに対し社員感情として不満や不服の「声」が出ています。東日本ユニオンが主張するベースアップの社員「一律」支給の根拠である「職責の重さは職制に応じて『昇格』『昇給』で保障されている」「職制に関係なく、社員は等しく職責の重さを背負い努力し奮闘してきた」「物価高騰は全社員共通の問題であり、職制や職責の重さは関係ない」「ベースアップ額を『一律』にしないと賃金制度に矛盾する」「ベースアップで格差をつけると、同じ職制同士でも賃金に差が生まれる」ことを、すべての社員が共通の認識とし、その解決に向けて取り組んでいこうではありませんか。 今2024春闘は、賃金引き上げに対して「さらなる営業収益の確保とコストダウンが必要な厳しい経営環境である」「中長期的な動向等を勘案して慎重な判断が必要である」とした経営側のネガティブな姿勢からのスタートでした。「統一行動」により、連日各地から寄せられた社員の「声」は、物価高に直面する生活の苦しさ、高まる労働密度に見合っていない賃金、会社だけが成長し続けることへの不満。そして今春闘において社員が大切にされていると実感できる賃金引き上げを求める「声」が結集し、労働側の大きな団結をつくりだしました。その結果「賃金は労働条件の最たるものであり、社員のモチベーションの向上につながる」ことを経営側に認識させ、要求額に迫る回答を勝ちとることができました。 組織の総力をあげて、労働者の団結で2024春闘を共に闘い抜いた成果を全組合員で確認します。 労働組合未加入の社員のみなさん 東日本ユニオンに加入して、私たちと一緒に、社員が安心で安定した人生設計や明るい将来を語り合える賃金をはじめとした労働条件の向上を実現していきましょう。 これまでの取り組みに感謝を申し上げ、2024春闘妥結に関する中央執行委員会見解とします。 2024年3月15日 JR東日本労働組合 中央執行委員会 |
|
■ 第3回団体交渉 (2024年 3月 8日) |
|
第3回団体交渉は2024年3月8日。経営側より回答を受けました。
★口頭回答 現行制度で妥当であり、廃止する考えはない。
|
|
■ 第2回団体交渉 (2024年 3月 5日) |
|
第2回団体交渉は2024年3月5日。定期昇給の完全実施やベースアップの実施、第二基本給の廃止について強く訴えました。 ●昇給係数4での定期昇給実施について <組合側の主張>
<経営側の主張>
●ベースアップの実施について <組合側の主張>
<経営側の主張>
●社員一律によるベースアップの実施について <組合側の主張>
<経営側の主張>
●第二基本給の廃止について <組合側の主張>
<経営側の主張>
|
|
■ 第1回団体交渉 (2024年 3月 1日) |
|
第1回団体交渉は2024年3月1日。組合側から要求の趣旨説明を行うとともに、経営側から現状認識の説明を受けました。
◆ 組合側の要求趣旨説明(要旨) ○2024春闘交渉における基本スタンス 経営側が新賃金・夏季手当について同時議論したいとする提起に同意することはできない。その理由として
以上のことから、今団体交渉においては「令和6年度夏季手当」について同時議論は行わない。
〇一律要求の根拠 年齢や職制によりベースアップに格差をつけることは認められない。 職責の重さに見合った処遇や社員の成長意欲に応えることは人事・賃金制度で保障されており、さらには管理手当等の見直しで優遇されている。 社員を取り巻く現状に年齢や職制、職責の重さは関係ない。 ベースアップは社員一律により実施することを強く求める。
○社員の奮闘を正しく認識すべき 昨年7月の秋田県を中心に記録的な大雨、2024年元日の能登半島地震では、多くの鉄道設備に被害を受けた。 社会的な影響を最小限に抑え、被災地域や市民生活の復興にむけた公共交通機関としての役割を果たしてきた。 いまもなお、生活の復興に向けて奮闘している社員や家族がいることを経営側は忘れてはならない。
○働き方の実態に見合ってない賃金 「新たなジョブローテーション」による異動に伴う遠距離通勤や単身赴任、希望もしていない担務への変更にも応じ、経済的、精神的負担を伴いながら、労働密度だけが高まり続けている。 効率化や生産性の向上として業務に必要な要員が削られ、求められる役割や仕事は増えているにも関わらず、賃金が増加しないことから不満は募る一方である。
○物価高騰に追いついていない賃金 現在の当社の賃金水準は相次ぐ生活必需品の値上げをはじめとした歴史的物価高騰に追いついていない。 2023年12月の毎月勤労統計で実質賃金は前年比1.9%減で21ヶ月連続のマイナスだ。 2024年2月の飲食料品値上げは1,626品目にも上る。今後物流の「2024年問題」に対応した物流費の大幅な上昇が見込まれる。 当社の平均基本給は2019年度の294,881円から2022年度は291,534円となり、約3,300円低下した。 2023年度に賃金改定はしたものの、2021年度に「昇給係数2」とした影響により、世間動向より当社の実質賃金の低下は著しい。
○止まらない離職 求められる業務内容や業務量と賃金のアンバランスから離職も相次いでいる。 心身を病んでしまう社員も後を絶たない。
○施策の独り歩きは労働意欲の低下と労働災害へのリスク増 会社主導の施策が社員の発意にすり替えられ、挑戦を押し付けられることにより施策そのものが目的化されている。 現場の「自ら考える」とした判断力も失われている。その結果、労働時間の改ざんや賃金の未払いなどのコンプライアンス違反が各地で発生している。 また、休日出勤を発生させることとなり、要員を逼迫させている。その先に待っているのは、労働意欲の低下、労働災害を含めた大きな事象を生み出すリスクの増加である。
○ベースアップをしない理由は存在しない!満額回答を求める! 社員は、この間の収入減や歴史的な物価高騰による生活苦、官民あげての賃金引き上げに向けた世間動向、好調な足元の業績もあり、大幅な賃金引き上げを期待している。 社員一丸となってベースアップ議論ができる経営環境をつくってきた今日、経営側が基本給改定を実施しない理由は存在しない! 社員とその家族が安心して生活ができるよう満額回答を求める!
◆ 経営側の現状認識と基本的スタンス(要旨) 貴側から新賃金の要求しかいただいていないが、お伝えした通り、新賃金と夏季手当について議論を進めていきたいと考えている。 第3四半期決算は社員の努力やお客さまのご利用回復により単体で2297億円の黒字を計上し、1月の鉄道収入も対前年110%ではあるが、平日の新幹線のご利用の回復の遅れや能登半島地震の影響などから、中長距離収入は当初の計画を下回っている。 基本給は職責など様々な要素や業績、経済動向などの社会的状況等を踏まえ、総合的に勘案して決定する。 基準内賃金の引き上げは長期にわたり総額人権費に影響を及ぼすこととなる。足元の状況を踏まえつつ、中長期的な動向も勘案して慎重な判断が必要である。 |
|
■ 申21号として賃金改善の要求を提出 (2024年 2月13日) |
|
2024年賃金引き上げ要求の提出は、2024年2月13日。申21号・2024年賃金改定に関する申し入れとして経営側に提出しました。
2024年賃金改定に関する申し入れ (2024年2月13日申し入れ)
経営側は1月31日に「2024年3月期第3四半期決算」を発表しました。通期業績予想を上方修正する内容であり、連結・単体ともに好業績な結果となりました。その要素の一つには、お客さまのご利用状況が着実に回復したことから、大幅な増収・増益へとつながったということもありますが、様々な会社の施策の導入に伴って社員の業務量が増加している中でも、一人ひとりがその働き方に応え、奮闘した結果であることは間違いありません。 社員一人ひとりが、日々お客さまの安全を守り、サービスの向上を目指して、取り組んでいることで会社が持続的に発展していることを経営側は直視するべきです。 現在の当社の賃金水準は生活必需品の相次ぐ値上げなどの歴史的物価高騰に追いついていません。 この間、各地の職場から東日本ユニオンにJR労働者の多くの声が寄せられています。それは労働組合に所属していない社員のみなさんの本音であり、この間の「昇給係数2」という定期昇給や期末手当の支給額に対する不満や悲痛な叫びでもあります。 したがいまして、東日本ユニオンは社員が安心した人生設計や将来を考えることのできる賃金を求め下記の通り申し入れます。
記
以 上 |